【考察】『鬼滅の刃』刀鍛冶のルーツは熊本にあり?人吉球磨の製鉄神話と大蛇伝説の深いつながり
郷土史家 前田一洋先生に聞く人吉球磨の伝承第二話『人吉球磨の製鉄の歴史と大蛇伝説』。先生の話を聞くうちに繋がる『鬼滅の刃』のキャラクターたち...。ルーツは人吉球磨にあった!?

おるたー、かのんです。
前回、「タロージイタチ」という人吉球磨の面白い伝承を教えてくださった郷土史家の前田一洋先生が、今回は「鬼滅の刃」に関連したお話をお話を聞かせてくださいました。
前田先生、「鬼滅の刃」の2期「遊郭編」が終わり、3期は「刀鍛冶の里編」だと発表されました。
主人公・竈門炭治郎の日輪刀を作ってくれる刀鍛冶・鋼鐵塚蛍(はがねづか・ほたる)さんは「ひょっとこ」のお面をしています。
この「ひょっとこ」は、人吉球磨地方と関係あるそうですね。「ひょっとこ」と「おかめ」は全国区じゃないんですか?
もちろん全国区だけど、人吉球磨にも関係が深いとたいね。
ひょっとこの由来は知っとるね?
「火男(ひおとこ)」でしょう。
火をフーフー吹くために口をとがらせている、と聞いたことがあります。
『鬼滅の刃』刀鍛冶の里と「ひょっとこ」の意外な関係
ひょっとこの面のルーツは製鉄職人の崇高な姿
その火は何の火?
な、何の火って!?
えーっと、どじょう鍋のためにお湯を沸かしているとか?
どじょうすくいとは関係無かよ。
あ、「刀鍛冶の里」では全員ひょっとこのお面。もしかして、鍛冶屋さん?
それだ!
もともと「ひょっとこ」は片目がつぶれて口がまがっているが、それは「鑪炉(タタラロ)」という溶鉱炉で製鉄をする男の姿なんだ。
映画『もののけ姫』でタタラを踏んでいるのは女性たちですが……。
それはアニメだからだろう。本来、女性は入ってはいけない。女神が怒るからね。
木炭と砂鉄を燃やし、温度を上げるためにタタラで風を起こし、鞴(ふいご)で溶鉱炉に風を送る。
質の良い鉄を製造するために、責任者は溶鉱炉の中の火の状態を厳しくチェックしないといけない。
狭い窓から溶鉱炉の中を覗くには、カメラで撮影する時のように片目をつぶるはずだ。
長年、高温の炎を凝視していれば目はつぶれるし、熱で唇はゆがむだろう。
それは鉄を作る男たちの崇高な姿であり、尊敬の的だったんだよ。
それじゃ、片目をつぶった「ひょっとこ」のお面などは、ベテラン鍛冶職人を忠実に再現しているってことですね!
「刀鍛冶の里」の人々のひょっとこ面は両目ですが、鋼鐵塚さんは鬼のせいで失明してしまうんですよ。片目だけ。
うーん、それは火男の運命(さだめ)かもしれん。
出雲地方(現:島根県)では、製鉄をおこなう責任者である「村下(むらげ)」は、神様扱いだった。
良質の鉄を製造するには、村毛の長年の勘と技が必須だからね。
しかし時代が下ると共に、その価値が忘れられ、「ひょっとこ」のような化け物やおどけ者に格下げされてしまったんだよ。
カッパだって、かつては崇拝の対象だったのにね。
昔は「川で泳ぐとカッパに尻子玉を取られる」と恐れられていたようですね。
どちらにせよ、今では本来の価値観が忘れられ、“崇拝”や“尊敬”の対象ではなくなったんでしょうね。
人吉球磨に伝わる「片目」と「大蛇」の伝説
神の化身「片目の魚」と祇園さんの祟り
「ひょっとこ」と同じように、目に関係あるのが「片目の魚(うお)」たいね。
川辺川(かわべがわ)や、球磨川支流である鳩胸川(はとむねがわ)上流の人吉市赤池町あたりで、もし片目の魚が網にかかったら、
「大変申し訳ありません。失礼いたしました」
とお詫びしながら、逃がさなければならない。
川辺川上流の「祇園(ぎおん)さんの池」(球磨郡五木村瀬目)のような、年中、水温・水量が一定のところにも片目の魚はいるらしい。
「片目の魚を食べたりしたら、大変なことになる」という伝承があるとたい。
大変なことって?
とんでもない不幸に見舞われる、ということだろうね。
祇園さん、つまり八坂神社の神様の化身を口にするなんてバチ当たりだからね。
五木村教育委員会の木野徹也さんによると、「祇園さんの池」は、今では埋め立てられてしまったそうなんだよ。
川辺川の、このあたりが、かつて祇園さんの池だったところだね。
祇園さんの池には、片目の魚がいたんですか。
「片目の魚を食べた人が何人か亡くなった」とか、「祇園さんの池の埋立に関わった人は不幸続きだった」とか、色々な話が残っているんだよ。
それ、いわゆる「祇園さんのたたりじゃ~‼」ですよね。
本当にたたりかどうかは別として、片目という点では、「ひょっとこ」と同じ。神様に近いと考えて、畏怖していたのでしょうか。
そうかもしれんね。
祇園さんの池のそばにも、銅の鉱山があった。採鉱冶金に携わる人が目を傷めたのではないかな。もしかしたら、鉱毒の影響だったかもしれんし。
とにかく片目であることは畏敬されこそすれ、マイナスには働かなかったということだね。
お姫様をさらった大蛇と「鱗滝」の名の謎
ところで、道の駅人吉クラフトパーク石野公園(人吉市)のそばに、ポットホールの「カマノクド」があるね。
自然にできた甌穴(おうけつ)ですよね。
熊本県天然記念物の。
同じ鳩胸川の2kmほど下流、下篠橋(くだしのばし)に行ってみよう。
この橋の先にある一丸(いちまる)集落で、お姫様が大蛇にさらわれた伝説が残っている。
えっ、お姫様が!?
田山(たやま)さんという大きな屋敷に住んでいる人がいて、とても美しいお姫様がいたそうだ。
その姫が、ネギを洗うため「下篠の轟(くだしののとどろ)」(球磨郡錦町)に行った。
轟(とどろ)とは、滝のことだ。
ネギ洗い姫⁉
桃太郎のおばあさんみたいじゃないですか。
お金持ちのお嬢様だけど、よく働く姫だったんだろう。
この辺の岩の上で泥を洗っていたと思われる。
なんて美しい、のどかな錦町。
滝つぼで姫がネギの泥を洗っていると、流れて来たのが……。
桃でしょ⁉ 「剣豪とフルーツの里 錦町」の名産が、どんぶらこと……。
いやいや、流れて来たのは、朱塗りの木の器だよ。球磨・人吉地方では「ゴキ」と呼ぶ。
姫がそれを取ろうと手を伸ばしたその時、川からザバァ~ッと大蛇が出て来て、姫をさらって行ったんだ。
姫の帰りがあまりにも遅いので、心配した父親は川に見に行った。短刀を口にくわえて、警戒しながらね。
するとネギのカゴが放り出してあるじゃないか。父親は、娘が滝に落ちたのではないかと思い、淵をのぞき込んだ。
すると大蛇が現れ、滝に大きな声が響き渡った。
娘は俺がもらった。
代わりに俺のウロコをやるから、大事にせよ。
これがあれば、おまえの家はますます栄えるであろう。
ただし、ウロコは決して人に見せてはならぬ。
口外してもならぬぞ。よいか。
そして大蛇は、滝つぼに消えていったと伝わっている。
えっ、ウロコ? 滝つぼ?
炭治郎の剣士の先生は、もと水柱の「鱗滝左近次(うろこだき・さこんじ)」さんですよ。
お面かぶっているし!
いや、鱗滝さんは天狗面だけど。
絶対、鬼滅と関係ありますよ!人吉や球磨地域は!
面白いね。今では下篠の轟では神様を祀って、公園のようになっとるよ。
公園の近くにお墓がいくつかあるけど、「田山家」はないなあ。
この小さいお地蔵様は、お姫様のお墓かもしれんね。
ウロコのおかげで田山家はますます繁栄したんでしょう。どこかに引っ越して行かれたのかもしれませんね。
そうだね。でも、何代目かの時に火事になり、
さらに災難続きだったと聞いているよ。
あれ、前田先生がご存じだと言うことは、田山さん、大蛇との約束を破って他人に言っちゃったんですね。
家族の誰かが、自慢話をしたんだろうね。
ウロコなんてお宝、鑑定団に出したくなりますよ。
全ての伝説は「製鉄」に繋がる – 鬼滅と神話の考察
この大蛇も、製鉄と関係があるったい。
まさか、ネギ姫誘拐事件は「ひょっとこ」の話の続きだったんですか?
そのとおり。製鉄して、鉄ができあがったら、溶鉱炉を壊して鉄を取り出さねばならない。
溶けた鉄がドロドロと流れ出る様子を、くねくね動く「大蛇」に見立てたのではないかな。
人吉球磨地方で「大蛇」「片目の魚」「ひょっとこ」などにまつわる伝承が残っておるが、これらはすべて製鉄と関係があると思われる。
お姫様がいた一丸集落の隣にある無田原(むたはる)集落に行った時のことたいね。
そこで出会った男性が、たまたま私の親戚だとわかり、訪ねて行ったんだ。その人が「うちの近くの畑から、役立たずの石がゴロゴロ出て来る」と言うので、見せてもらった。
すると石ではなく、なんと鉱石から鉄を取った時に出るスラグというカスだった。しかもフイゴ(風を送る道具)の羽口まで出て来たよ。
一丸集落や無田原集落あたりで製鉄が行われていた証拠じゃないですか!
ヤマタノオロチ神話と出雲から伝わった技術
前回、「タロージイタチ」の話の時に「牛頭天王(ごっどん)」のお札の話をしたね。
牛頭天王とは神仏習合で、スサノオノミコトのことを表すんだよ。
スサノオが退治する八岐大蛇(ヤマタノオロチ)も姫をさらう話だが、これも製鉄と関係あると思うとたい。
あれ、スサノオノミコトがヤマタノオロチをやっつけて、お姫様を助けたのは、確か出雲の山ですよね。
さっき、「出雲では製鉄をおこなう責任者は神様扱い」って……。
そう、出雲。製鉄法は、もともと出雲からもたらされた。
出雲で製鉄の修業をした人が、球磨地方にもやって来たんだ
田山さんなど地域の有力者に「製鉄に協力して」と頼む時に、神がかった話をしたんじゃないかな。
既にお金持ちだから、「もうかりまっせ」と言うより、「神への奉仕」と言った方が、有力者たちも協力する気になったのかもしれませんね。
修験者たちが集めた情報と医療の役割
全国を自由に行き来することが禁じられていた時代に、鉱石を探し回って採掘するなんてことができたのは、修験者のみ。
高野山(和歌山県)、熊野(和歌山県)、英彦山(福岡県)などの修験者たちは修行も兼ねて道なき道を進み、情報を得る。
また集落に拠点を作って、それを「権現様(ごんげんさま)」として祀った。
その権現に滞在しながら、地元の人々のケガや病気の治療をしてやったり、地鎮祭をしたりして、情報も集めていたんだよ。
「富山の薬売りは、全国で情報を集めるスパイだった」という説を聞いたことがありますが、修験者は、もっと偉い位置づけですよね。
何しろ、神仏に仕える身分だ。それに山の中を移動するわけだから、体調を崩した時のために、薬草などの知識も豊富だっただろう。
最新の治療法を駆使して、各地域の人に医療を施したと思われるから、尊敬されただろうね。
「ひみつ基地ミュージアム」(球磨郡錦町)に、戦時下に「高原(たかんばる)飛行場」(海軍人吉飛行練習場)だった跡地があるよね。
その南西部、球磨川と川辺川の合流地点あたりに相良村の井沢集落があり、そこに「井沢権現社(井沢熊野座神社)」がある。そこも、かつては修験者の拠点だった。
地元では「権現さん」と呼ばれて親しまれていますが、日本遺産人吉球磨の構成文化財の一つですね。
祀られているのは、16世紀に作られた役行者(えんのぎょうじゃ)像。修験僧がモデルだそうですが。
そう、私が『相良村史』の編纂をしていた頃、隠されたご神体を見せてもらうと、薬師如来の絵が描かれた板があった。
そして仏像と一緒に「ケシ」の文字があったんだ。
民謡「球磨の六調子」の歌詞に、
「♪親がくれても井沢にゃ行くな。井沢 ヤンボシ原(わら) ケシ畑」
とある。
「ヤンボシ原」とは「山伏のいる所」という意味だ。つまり「井沢の山伏がいる所にポピーの畑がある」と。
ポピー? 丘の上のひなげしの花で、「好き」「嫌い」とか花占いするわけじゃないでしょう。
屈強な山伏たちが……。
いや、茎に毛のあるケシは安全だが、毛の薄いものは、麻酔薬モルヒネの原料アヘンを採るための植物。茎に傷をつけて出た汁がアヘンで、それを精製したらモルヒネになる。
それを使って、村人の病気を治したり、手術などの医療行為をしたりしたんだろう。
農林業などでケガを負った時、「井沢の山伏どんに頼めば、痛みもなく治してくれる」と評判になれば、人が集まり、修験者が知りたい情報もたくさん集まる。
ケシをいぶして煙を吸わせれば、気持ちよくなって、ストレス解消になったんだろう。
具合が悪けりゃ権現さんへGO!
老若男女、みんなが集まったんじゃないですか。しかもリピートしそう。
山伏はそうやって「猩々緋鉱石(しょうじょうひこうせき)が採れるのが〇〇山」などの情報もゲットしたんですね!
「片目の魚」を食べて体調が悪くなるのは神罰なので、権現さんに行くと悪化しそうですね。それとも、慈悲深い心で治してくださるのでしょうか。
さあ、それはどうかな?
現在では、園芸種のポピーは栽培していいが、アヘンのもととなる種類のケシは法律で栽培が禁止されているから、ご用心!
次から、『鬼滅の刃』『もののけ姫』を見る時も、アグネス・チャンさんの「ひなげしの花」や民謡「球磨の六調子」を聞く時も、今までと違う気持ちになりますね。
この記事のまとめ
- 『鬼滅の刃』の刀鍛冶が着ける「ひょっとこ」の面は、高温の炉を見続けた製鉄職人の崇高な姿がルーツであるという説があります。
- 育手「鱗滝左近次」の名は、人吉球磨に伝わる大蛇伝説のキーワード「ウロコ」と「滝」に由来する可能性があります。
- 「ひょっとこ」「片目の魚」「大蛇」といった人吉球磨の伝説は、すべて古代の「製鉄」文化に繋がっており、作品の背景を深く理解する鍵となります。
- これらの伝承や技術は、出雲地方のヤマタノオロチ神話や、全国を渡り歩いた修験者の活動とも深く関わっています。
【次回】
県境を越えているの? いないの? 薩摩藩 VS 相良藩、3つもある県境の秘密。
乞うご期待!

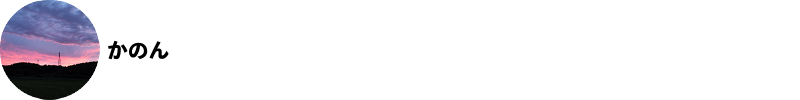
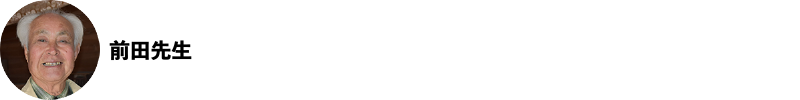








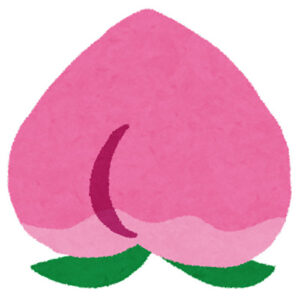

























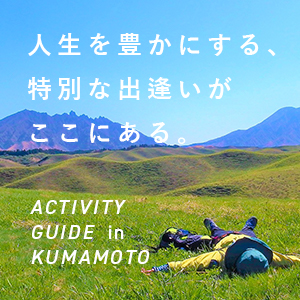
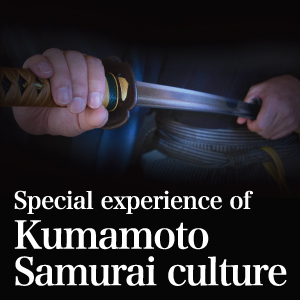
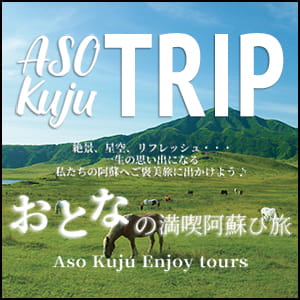











コメントをしたい方はこちらから