【肥後遊記】第拾四譚 『肥後のふしぎなもん』九州が誇る「キジ馬」の魅力!国選択無形民俗文化財に答申された人吉・球磨の伝統工芸とは?(人吉・球磨地域)
日本の郷土玩具の西の横綱「キジ馬」が、国選択無形民俗文化財に答申!鮮やかな彩色と独特の形が特徴の人吉・球磨のキジ馬は、平家落人伝説とも関わりが深いとされる伝統工芸。歴史や種類、地域ごとの違いを知れば、あなたもキジ馬の奥深い世界に魅了されるはず!

肥後(熊本)のふしぎなもんの仲間を求めて、津々浦々を旅している妖怪ひーでございます。
今回は、朗報があったばかりであり、郷土玩具界では東の横綱「こけし」に並び立つ、西の横綱「キジ馬」(人吉市)を紹介します!
キジ馬は、熊本県内では人吉・球磨地域で主に作られており、2025年1月24日に「九州地方のきじ馬・きじ 車ぐるま 製作技術」を、国選択無形民俗文化財(記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財)に選択するよう、文化審議会から文化庁長官に答申が行われたことでニュースになったこともあり、ご存知の方が多いのはないでしょうか?
1.「キジ馬」とは?
キジ馬(キジ車)は、主に九州の熊本県と福岡県、大分県を中心に作られている郷土玩具で古くは約30個所の製作地がありましたが、現在では約10個所程となっています。また、キジ馬は、その彩色や形状等で大きく3つの系統(人吉系、福岡県の清水(きよみず)系、大分県の北山田系)にわけられます。
各系統の特徴
| 系統 | 彩色 | 車輪の数 | その他 |
| 人吉系 | 赤、黄、緑 | 2つ | |
| 清水系 | 赤、緑 | 4つ | 背に鞍のようなものがある |
| 北山田系 | 彩色せず | 2つ |
また、大きさは、小さいものは手乗りサイズのものから、大きいものだと子どもが跨がれるようなものまであります。
キジ馬が作られるようになった由緒等は、平家の落武者と関係するとする説やお寺の創建に関わる伝説に登場したためとする説など、各地で様々なものが伝承されています。
また、キジ馬の記録として一番古いものと言われているのは、江戸時代後期、文政年間の好事家(こうずか)たちの会合の記録『耽奇漫録(たんきまんろく)』で、「雉子車」が出てきます。ここでの、キジ馬は、「筑後柳川産子とものもて遊ひもの」と説明されているので、と清水系のキジ馬だと思われます。
人吉のキジ馬(熊本県博物館ネットワークセンター所蔵)
※左:宮原工芸 作
※右:住岡郷土玩具製作所 作
2.人吉・球磨のキジ馬
人吉・球磨地方のきじ馬は、前述のとおりカラフルで2輪であることが特徴で、松の車輪をつけたものが有名です。今現在、人吉市の『宮原工芸』(人吉市)と『住岡郷土玩具製作所』(球磨郡錦町)がその技を継承されており、今でもこのきじ馬を購入することができます。
そもそも、この人吉・球磨地方のきじ馬は、どのように作られ始められたかは、定かではありませんが、一説によれば平家の落武者と関係するとする説があります。
平安時代の熊本県は、平清盛が直轄地として支配するなど、平家とは深い関係のある場所でした。そのため、源平合戦で敗北した平家が九州山地に落ち延びた平家落人伝説が県内各地で伝承されています。人吉地方でも、この地方に逃げた平家の落人たちが生活の糧として、また都の栄華を偲んで作り始めたと言われており、これがキジ馬の由来とされています。
なお、額部分に「大」とデザインされているのは、京都の大文字焼きからきているとするものや作り方を伝承した大塚家に感謝する印との話もありますが、戦前には「大」以外にも中小のものや無印のもの、五木村で作られたものには「五」のデザインがなされていたことから、定かではありません。
そんなキジ馬ですが、明治時代頃に一時期衰退に危機になりました。そこで、明治時代後期に住岡玩具製作所の初代・住岡喜太郎さんが、きじ馬を復興させ、現在でも販売されています。
元々、毎年2月に開催される人吉のえびす市の露天で、きじ馬や花手箱が販売されており、きじ馬を男の子に、花手箱を女の子に土産物として買って帰るのが習わしとしていたようです。
3.キジ馬? キジ車?
キジ馬とキジ車は、制作地や時代によってその表記に違いがある。ただ、現在、人吉球磨地域のものは、キジ馬と呼んでいます。畑野栄三著『日本の民芸 きじうま聞書』によれば、キジ馬は子どもが坂などの傾斜地で馬乗りして遊んでいたため2輪の「馬」であったものが、平地で引いて遊ぶようになり4輪の「車」と変化したのではないかとする仮説がたてられています。
あわせて、キジの文字も、鳥の「雉」とする説や「木地」をあてる説があります。人吉のものなど、彩色されているものは「雉」が近いように感じるが、大分のものは彩色を施さない「木地」を活かしてものとも言えるが、諸説あります。
4.キジはいないが、ウズラはいる。宮崎県の「うずら車」
九州の多くでキジ馬(車)は生産されているが、宮崎県ではみない。しかし、似たような存在として、「うずら車」があります。
うずら車もその起源とする説は様々で、久峰観音の開基に伴う百済の僧が伝えたや平家の落人伝説に関するもの等があります。一説には、久峰地区に住んでいた木挽衆が熊本県の湯前町から土産として持ち帰られていたものを、名前をキジからウズラに変化させて、久峰観音の縁日に合わせてお守りとして売り出したという説があります。
【NEXT】
【肥後遊記】第拾伍譚 『肥後のよかとこ、あんなとこ』
日本三大仇討ちの一つ「曾我兄弟の仇討ち」の供養塔?岩坂層塔(大津町)
お・ま・け
そのほか、県内の郷土玩具
熊本県内には、肥後こま(熊本市)、おきんじょ人形(八代市)、宇土張り子(宇土市)、花手箱(人吉市)、彦一コマ(八代市)、おばけの金太(熊本市)、木の葉猿(玉東町)等のように、各地の歴史や文化の中から生まれたもので、各土地の伝説や信仰等を反映等しながら作られてきました。作られる目的は、子どもたちの健やかな成長を願うものから、お土産品等と様々ですが、現在でも多くの郷土玩具が作られています。
県内では、この郷土玩具を買ったり、作る体験ができる場所が何か所かあり、熊本県伝統工芸館や、くまもと工芸会館、道の駅人吉等では職人さんから直接お話を聞いたりしながら郷土玩具を買ったりすることができます。






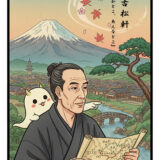














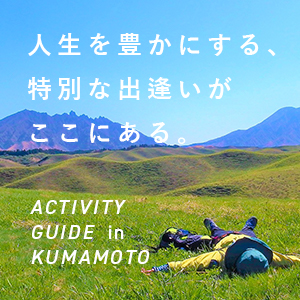
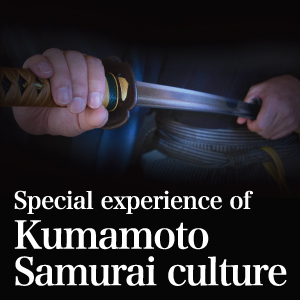
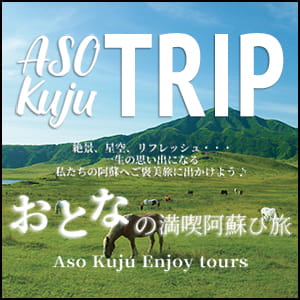











コメントをしたい方はこちらから